議事録の書き方で悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
社内、社外を問わず、会議や打ち合わせに参加する際、上司から議事録の作成を指示された経験はありませんか?
しかしながら、議事録の書き方について、しっかり体系立てて学べる機会はそう多くなく、議事録を書き残す目的を、正しく理解できていない人も少なくないでしょう。
議事録を作成することは、自身にとってのメモになるだけでなく、会社全体の利益に繋がる重要な施策と言っても過言ではありません。
誰が見ても読みやすく、分かりやすい議事録の書き方をご紹介いたします。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
目次
議事録が必要な理由
プロジェクトや組織の運営などについての重要な決定事項というのは、会議(ミーティング)で決まることがほとんどです。
しかし、関わるすべての人が会議に出席できるわけではありませんし、欠席者がでることもあるでしょう。
会議で決まった内容を正確に伝達するためには、口頭で伝えるだけでは齟齬や間違いがおきる可能性があります。
話し合いの要点や決定事項を正確に伝えるには、議事録が必要となるのです。
決定事項・経緯の共有
議事録の最も大きな目的は、関係者全員に決定事項を伝達することです。
会議に誰が参加し、どのような議題・議案について議論し、何を決定したのかという情報を、関係者に正しく共有する必要があります。
また決定事項を受け、今後すべきことも議事録には欠かせません。
具体的に「誰が・何を・いつまでに行うのか」などを項目ごとに分け、ToDoリストのように読み手に分かりやすく記載することが、議事録の書き方のポイントです。
備忘録として
議事録は、備忘録としての側面もあります。
同じ会議参加者でも、認識に齟齬があったり、聞き間違いや聞き洩らすことがあると、理解している内容や範囲が参加者ごとに異なってしまう場合があります。
また時間経過と共に、決定事項や、行うべきタスク、次回開催される会議の日程など、記憶に食い違いが起こることを防ぎます。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
見づらい、分かりづらい議事録の書き方になっている原因

せっかく作った議事録も書き方によっては、見づらい、分かりづらいと上司から指摘された経験のある方も多いかもしれません。
なぜ、分かりづらい、見づらい議事録となってしまっているでしょうか。
議事録が文字起こしになっている
議事録は、会議での発言を全て書けばいいものではありません。
例えば挨拶などの不要な情報を入れすぎることで、本当に必要な情報が埋もれてしまいかねないからです。
議事録にする際は、会議で話し合われた項目や内容を、簡潔かつ分かりやすくまとめることを心掛けましょう。
また議事録は会議での事実確認の資料でもあるので、事実のみを記載しなければなりません。
つまり主観的な意見や提案と、客観的な意見は区別して記載する必要があります。
事実のみを簡潔にまとめるための前提として、そもそも会議の目的が理解できていないと、記載しなくてはいけない内容が抜けてしまうということが起きるかもしれません。
何を決めるための会議なのか、議題は何なのか、まずしっかりと認識した上で、例え会議に参加していなかった人が読んでも、分かりやすく簡潔な議事録を作りましょう。
必要に応じて箇条書きにしたり、議題と決定事項を冒頭に持ってくるなどの工夫をすると見やすくなります。
発言者・責任者が誰か分からない
誰の発言かが明記されていないと、後で振り返った時に、言った言わないの問題になり、責任の所在が分からなくなる可能性があります。
また社外の人も含めた会議の場合、誰が発言したかで、その後の方向性が大きく変わる場合もあるため、発言社や責任者が誰であるか明記しなければなりません。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
会議の前から議事録の準備をしよう
議事録の担当者は会議の前にできるかぎりの準備をしておきましょう。
議事録を作成する担当者になった以上、会議にただ参加していれば良いということにはなりません。
事前に準備をすることで、後々の議事録作成のスピードや、クオリティのアップが期待できます。
会議の概要を確認しておく
会議の要点や目的、出席者などの情報をあらかじめ把握しておきましょう。
情報収集と事前準備が議事録作成のカギです。
会議の目的に応じて、議事録に記載すべき内容なども変わってきます。
懸案事項など事前に分かっていること、確認できる情報は必ず収集しておきます。
レジュメやアジェンダなどが事前に配布されているケースも多いと思いますので、確認するようにしましょう。
議事録の構成を決める
議事録を作成する際は、会議の内容を把握しつつ、得た情報を書き出さなくてはいけません。
白紙の状態でメモを取っていくという方法では、会議に追いつくことができなくなってしまうことも。
事前におおまかな構成を決めておくことで、項目ごとにまとまったメモを取ることが可能となり、後々、作業がしやすくなります。
アジェンダなどの資料を確認し、会議で話し合われる内容を事前にシミュレーションしておけば、会議の前に大まかな議事録を構築できてしまいます。
あとは、会議中に事前に作った議事録に決定事項や追記事項、注意事項、方針決定などの補足を書き込んでいきます。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
見やすい議事録の書き方のポイント

さまざまな立場の人が目にする議事録。
参加者や関係者だけに分かる内容ではなく、どんな人が見ても分かりやすい議事録をつくらなければいけません。
どうすれば見やすい議事録になるのか、ポイントをまとめてみました。
議事録のフォーマットを統一する
議事録は、枠組みや土台が出来上がったフォーマットがあらかじめ社内で用意されていたり、前任者が自作している場合があります。
毎回異なるものを使うと、内容の抜け漏れが発生してしまう可能性があり、読み手も読みにくいでしょう。
議事録は誰が読んでも分かりやすく作られる必要があるため、フォーマットは既存のものや、前回と同じ形式のものを使うと良いです。
具体的なテンプレート(見本)を作っておく
例えフォーマットがあったとしても議事録を作成するのを難しいと感じている人におすすめなのが、見本を作っておくことです。
何を書けばいいのか、フォーマットよりも細かく記載され、見本となるようなテンプレートを作っておくと、誰が議事録を作ることになっても、一定のクオリティの議事録が出来上がるので有効です。
会議の内容や議題(プロジェクトの進捗について、顧客への対応について、予算について、など)に応じて、いくつか具体的なテンプレートをつくっておき、その都度カスタマイズして使うと良いでしょう。
ベースを作っておくことで、素早い議事録作成が可能となります。
読み手が知りたい情報を簡潔に書く
議事録の主な読み手は、会議に参加しなかった関係者です。
そのため会議に参加しなかった関係者が読んでも理解できるよう、読み手の知るべき要点・要約を、正確に記録としてまとめることも、議事録の書き方のポイントです。
5W2Hを意識する
誰が見ても分かりやすい議事録を作成するためには、情報が整理されていることが大切です。
そのためにも、5W2Hに基づいた記載を心がけるようにしましょう。
| What | 会議のテーマ・議題・議案 |
| Why | 会議を開く背景、課題感 |
| When | 会議の日時、時間情報に関する決定事項 |
| Who | 会議の参加者・発言者、特定の対象者に関する決定事項 |
| Where | 会議の場所、または場所に関する決定事項 |
| How | 課題解決など方法に関する決定事項 |
| How much | 予算やコストに関する決定事項 |
このように議事録の書き方のポイントは、基本的に5W2Hを意識して考え、読み手に伝えることです。
この点に注意することで、間違った情報や誤解を与えにくい文章になるでしょう。
文書の見栄えを意識する
個人的なメモとは異なり、議事録は不特定多数の人が閲覧する記録なので、美しい議事録を心がけましょう。
部署を横断して共有することも少なくないため、誰が見ても同じ趣旨に伝わるよう、意識しなくてはなりません。
分かりやすい文を書く際には、主語と述語のねじれが起きないように注意しましょう。
あまり文字を詰めすぎず、意識して改行や分類を行います。
ページ数が多くなりすぎると、読みにくくなりますので、必要な情報を精査することも大切です。
情報にまとまりがなく、内容が散乱してしまわないように、まず議事録を書く前に、時系列や優先度を整理した上で、丁寧に残していくようにしましょう。
発言者を記載する際は、議事録冒頭に「敬称略」と断りを入れることで、例えば社長や取締役、部長などの役職や、人物に敬称を付けずに記載しても、マナー違反にはなりません。
発信する前に他者に確認してもらう
会議中は発言内容の抜け漏れなど、曖昧な部分が発生する場合があります。
議事録に不確実な情報を記載してしまうと、読み手も当然誤解をしてしまう可能性があります。
特に数字の間違いは、大きなトラブルに発展する恐れもあるため、慎重さが必要です。
一緒に会議へ参加した上司や同僚など、他者に内容を確認してもらうことを心がけ、必要に応じて、加筆・修正を行いましょう。
下書きを第三者にチェックしてもらった後で、清書を行うと無駄がありません。
なお発信後に、記載漏れや誤字脱字が発覚した場合、会議の種類によっては法的なルールに従って訂正版や差し替えなどを行わねばならない可能性もあるため、議事録が完成したら記載内容の不備がないか、他者に最終チェックしてもらうことがやはり重要です。
24時間以内に共有する

議事録は、会議終了後迅速に共有することも心掛けておきたいポイントです。
企業によっては議事録の共有までの時間が決まっているケースもありますが、一般的に、議事録の送付は24時間以内と言われています。
少しでも作業量を削減するためにも、会議名や日時、議題や発言者など、事前に分かっている情報は会議前に埋め、作業効率を上げましょう。
共有方法は、メールのほか、ITツールや社内ポータルサイトを利用して、必要に応じてオンラインで見られるようにしておくのがスムーズです。
議事録は多くの人が目にするため、素早い行動をすることで、自身の評価にもつながるかもしれませんし、記憶が鮮明なうちに情報を整理することで、効率的で正確な議事録作成が行えるというメリットも期待できます。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
正確で分かりやすい議事録の書き方
議事録の作成方法は「会議報告書」「株主総会」「理事会議事録」など、会議の種類によって大きく異なります。
それぞれの議題などについてしっかりと理解してから臨みましょう。
会議の議事録を正確に残すためにも、メモの取り方には注意が必要です。
普段の会議から議事録の取り方に意識することで、質の高い議事録を残せるようになります。
ノートやPCにメモを取る
議事録を取る基本として、ノートやPCに会議の内容を記録する方法があります。
会議終了後に効率的な議事録作成を行うために、メモを取る際には箇条書きや記号の活用がポイントです。
質問・回答のメモを取るときは、主語と目的語を必ず記すようにしてください。
もし分からない場合は、会議の場で確認し、主語と目的語を明確にしておくと後々困りません。
手書きの場合は詰めて書かず、余白を残しておくと、何か補足があったときにも追記しやすくなります。
見返すときに分かりにくくならないよう、項目ごとに分けてメモするなどの工夫が必要です。
PCでメモを取る場合は、自身にとって使いやすいエディタを見つけておくと良いでしょう。
また必要であれば図形やグラフなどを駆使し、決定事項を目立たせたりすることで、議事録をスムーズに書けるようになります。
ICレコーダーの活用
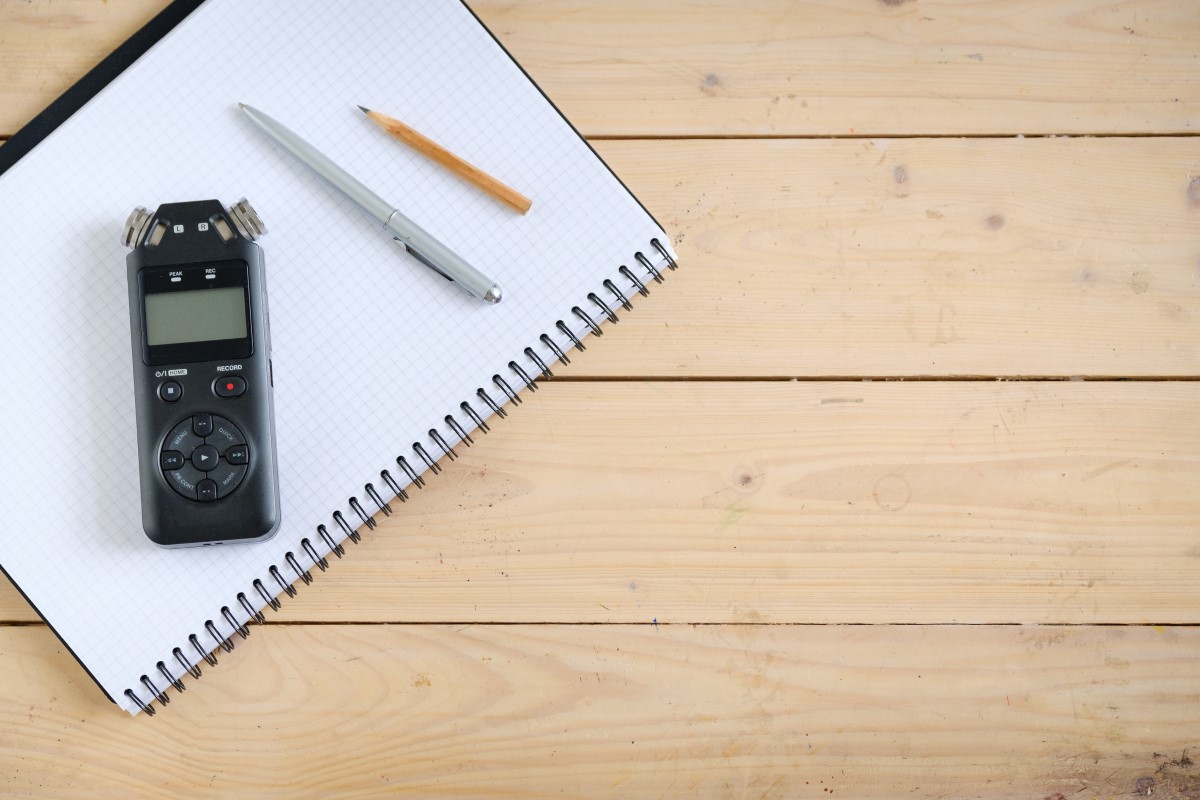
テキストでメモを残すだけでなく、ICレコーダーで記録しておくことも正確な議事録作成のための有効な手段です。
会議中、メモを取りながら会議内容を聞いていると、聞き逃しを起こす可能性があります。
ICレコーダーを利用し、会議内容を音声で記録することによって、議事録の抜け漏れを防止できます。
録音した内容を聞きながら議事録を作ることになるため、文字起こしにならないよう、注意する必要があります。
重要な案件や決定事項は、自分が分かりやすいように手書きのメモに残しておくなどの工夫をすると、後から録音を聞いたときに、要点が分かりやすくなります。
ITツールの活用
ノートやPCで議事録のメモを取ることが苦手な場合、ITツールの活用も有効です。
メモツール・チャットツールなどを利用することで、機械的にテキストデータを残すことが可能だからです。
PCやスマートフォンのアプリと連携することで、メモを参照しながらスムーズに議事録の作成を進められる場合もあります。
またExcel・Word形式で議事録を残したい場合には、ファイルストレージサービス等のツールも良いでしょう。
オンライン下であれば、時・場所を問わず、関係者への共有が可能となるため、テレワーク時にもストレスなく業務効率化に貢献できます。

タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
タスク・プロジェクト管理ツールJootoとは
Jootoは、タスクを可視化し、プロジェクトを管理するためのクラウドツールです。
プロジェクト進行に必要なタスクに、5W2Hの情報を盛り込み、プロジェクトチーム全体の共通認識として、リアルタイムに確認することができます。
つまり「報告・連絡・相談」だけでは補えないような、プロジェクトメンバー各々が抱えるタスクの詳細・期限・進捗状況を、ガントチャートで見える化できるのです。

Jootoなら、実際の会議シーンでも「活かされる議事録」としてご活用頂けます。
会議内において、新たなToDoが発生した場合、議事録を取るようにJooto画面上で、5W2Hの情報を盛り込んだ新規タスクを作成します。
議論の中で具体的な期日と担当者を決定し、参加者の合意形成を成すことで、認識の相違なく、会議の内容がプロジェクトに反映されるのです。
タスクはJooto上に残るため、プロジェクトメンバー全員でタスクを管理することができます。
会議に参加していない関係者にも、タスク内のコメント機能により、その経緯をタスク詳細として伝達可能です。
Jootoなら、会議内容をネクストアクションに繋げ、「活かされる議事録」としてご利用頂くことができます。
ぜひ、Jootoの導入をご検討ください!
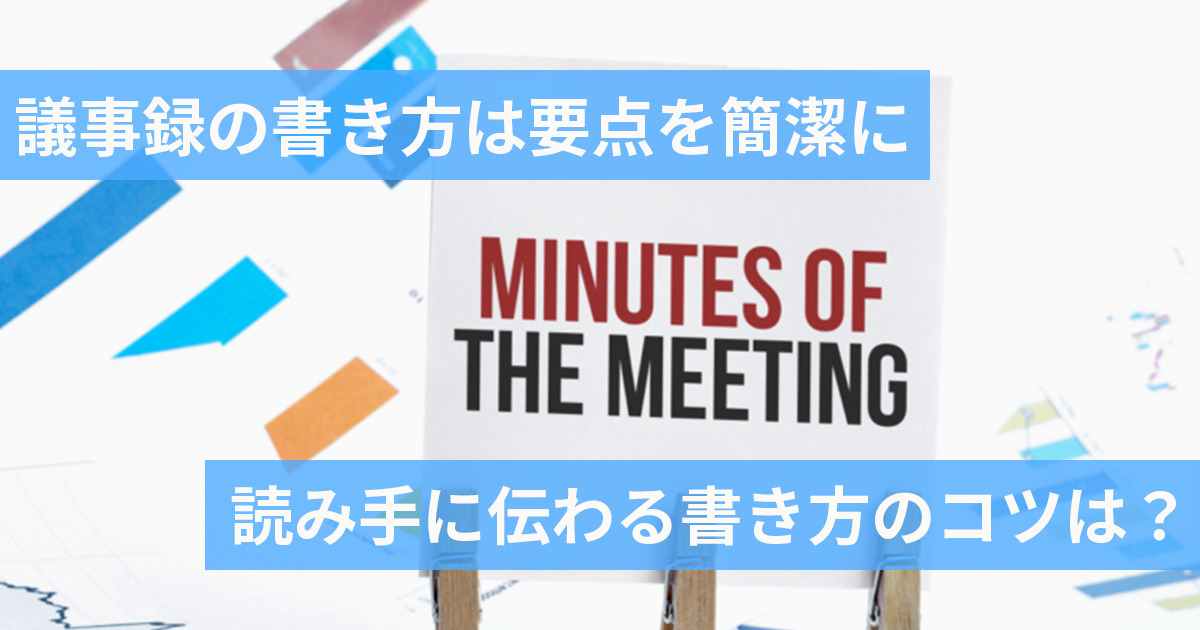
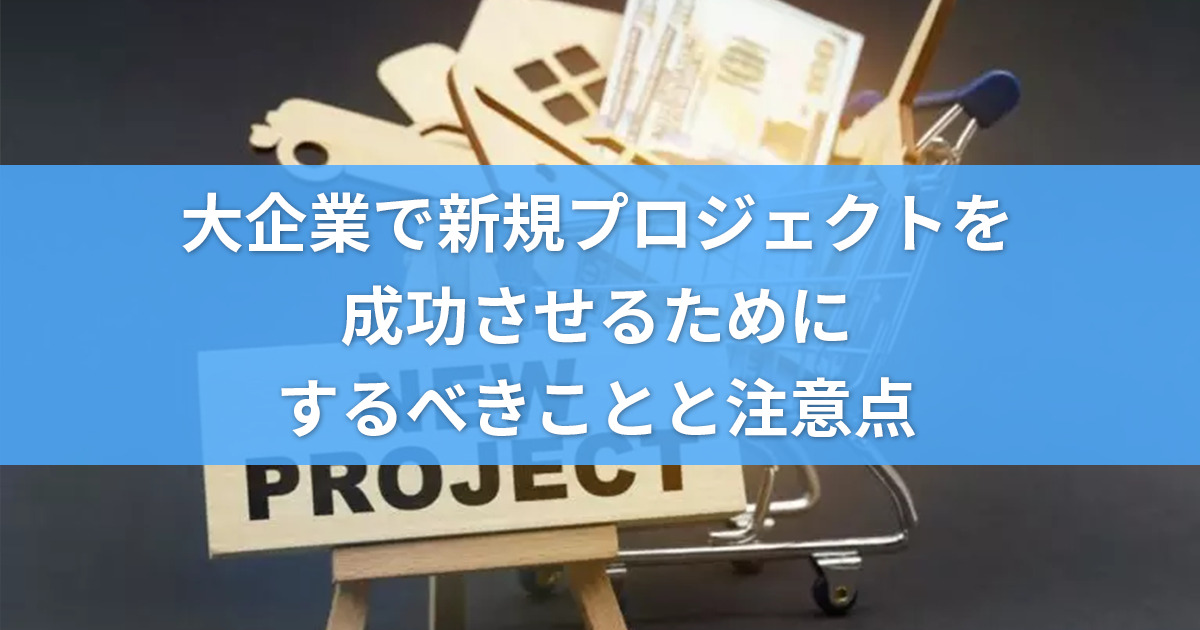
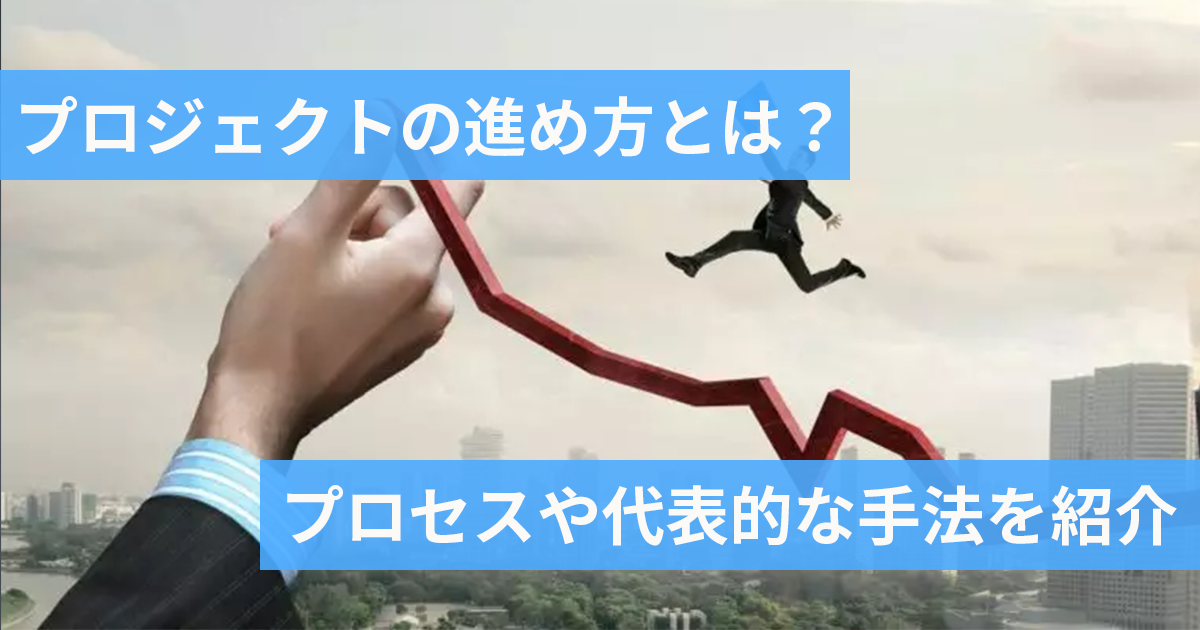
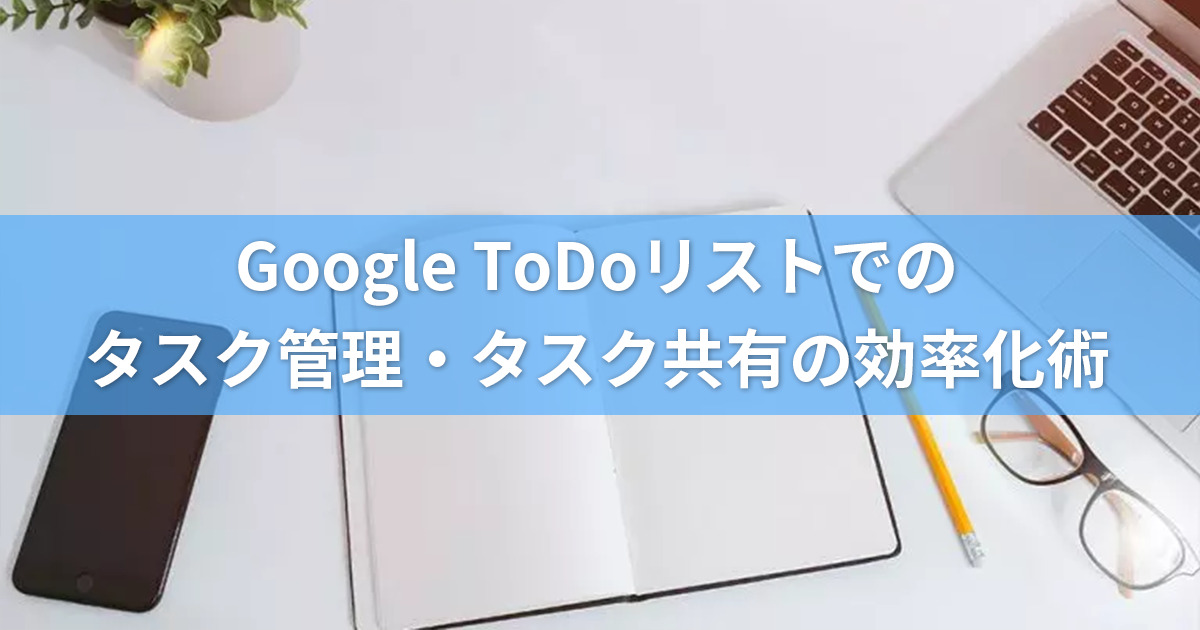
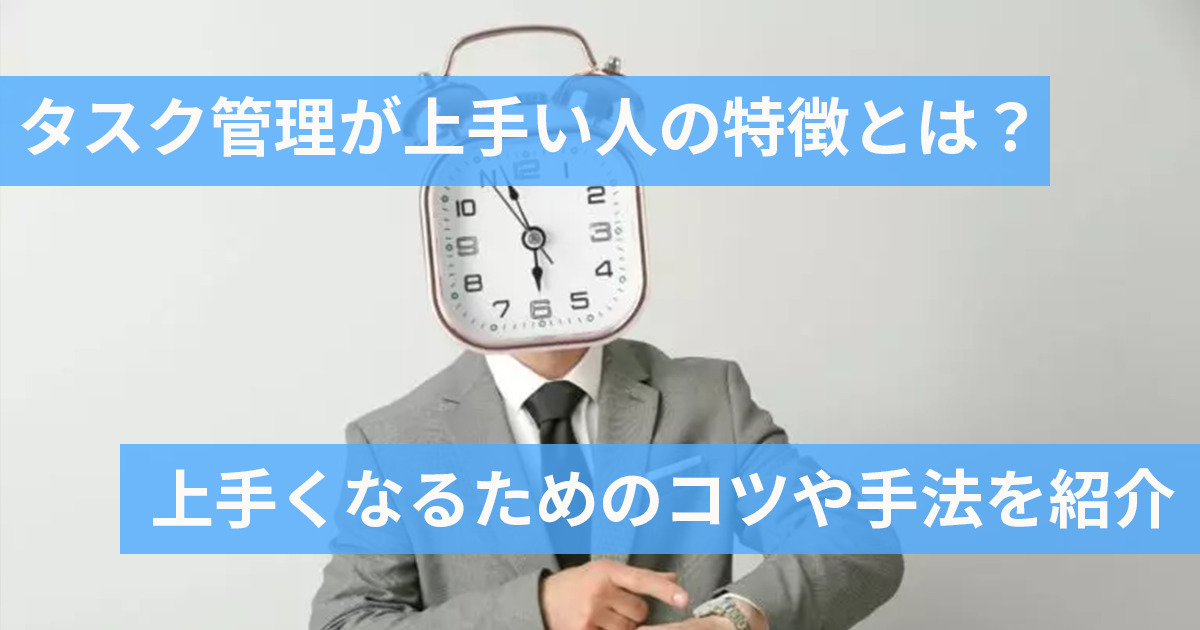

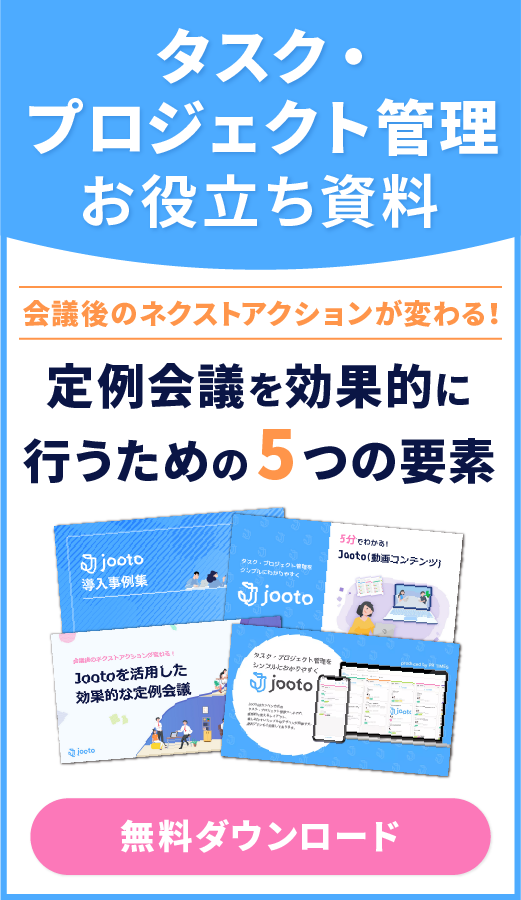
Comments are closed.