ビジネスシーンにおいて、ステークホルダーという言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
現在SDGsやCSR(Corporate Social Responsibility)など、社会課題に対する取り組みが企業に求められており、ステークホルダーが重視されています。
なぜなら企業はステークホルダーに対する責任や、利益を意識しながらビジネスをおこない、成長すべきだからです。
本記事ではステークホルダーの基本項目、ステークホルダーの考慮した企業施策やその方法等をご紹介いたします。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
目次
ステークホルダー(Stakeholder)とは
ステークホルダー(Stakeholder)とは、企業や組織の活動により影響を受ける利害関係者を指します。
一般的に「利害関係者」というと、経営者、株主、従業員、取引先など金銭的なつながりのある関係者を想像するかもしれません。
しかしステークホルダーの範囲は金銭的なつながりに限らず、企業や組織の活動により何らかの影響を受ける全てのものが該当するのです。
ステークホルダーの解釈の変化
ステークホルダーという言葉は、アメリカの哲学者エドワード・フリーマン教授が使用したことが始まりだといわれています。
そもそもステークホルダー(Stakeholder)とは、出資金(Stake)と保有者(Holder)を由来とし、元来「投資家」を意味している言葉です。
しかし今では解釈が拡大され、利害を共にする人や企業、団体、地域、社会なども含めて示すようになりました。
そのため近年では、企業が経営活動をおこなう上で、その地に生活基盤のある地域住民などのステークホルダーとの関係性を重視した経営理念を掲げる企業も少なくありません。
また利害関係者といっても、必ずしもお互いの利害が一致するとは限りません。
先ほどの例でいえば企業が経営活動をおこなう場 合、その企業で働く従業員は給与の増加や待遇改善を期待する一方、その地域社会は地元への貢献を望むでしょう。
つまり影響する利害は異なるものの、中心となる企業から影響を受けている限りステークホルダーとなるのです。
ステークホルダーの種類
ステークホルダーは企業や組織との関係性によって、以下の2つに分類することができます。
- 直接的ステークホルダー
- 間接的ステークホルダー
直接的ステークホルダー
直接的ステークホルダーは、企業の活動内容などに直接的な影響を与えたり、絶対的な権限を持っている人や団体であるとともに、企業活動によって直接的な影響を被る存在を指します。
具体的には経営者、従業員、クライアントなどの取引先、株主や顧客、金融機関などが直接的ステークホルダーに当たります。
間接的ステークホルダー
間接的ステークホルダーとは、企業の活動範囲やその内容に直接的な影響は与えないものの、間接的に影響を受ける人や団体、相互作用的に影響し合う存在です。
地域住民や地域社会、行政機関や政府、また従業員の家族も間接的ステークホルダーに含まれるでしょう。
ストックホルダーやシェアホルダーとの違い
ステークホルダーと混同しがちな言葉が「ストックホルダー」と「シェアホルダー」です。
上述のようにステークホルダー(Stakeholder)は、企業や組織によって影響を受ける存在を包括しているのに対し、ストックホルダー(Stockholder)やシェアホルダー(Shareholder)は「株主」と限定しています。
ストックホルダーもシェアホルダーも「株主」を指しますが、株主総会などで議決権を行使できるなど、企業の経営活動に影響を及ぼす大株主をシェアホルダーと呼びます。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
ステークホルダーを考慮した施策

ステークホルダーの解釈が拡大していくと共に、ストックホルダー、シェアホルダーのみならず、さまざまなステークホルダーと企業は信頼関係を結び、ステークホルダーを意識した経営施策が課題となっています。
こうしたステークホルダーを考慮した施策として代表的なものが、下記の2つになります。
- ステークホルダーエンゲージメント
- ステークホルダーマネジメント
ステークホルダーと良好な関係を築くための重要な手法です。
ステークホルダーエンゲージメント(Stakeholder engagement)
ステークホルダーエンゲージメント(Stakeholder engagement)とは、企業がステークホルダーの関心や期待を把握し、ステークホルダーの意思決定に寄与する手法です。
詳細としては、パンフレットやWEBサイトによる情報提供にのみならず、説明会や窓口設置などの直接対話、第三者機関などを通じたアンケートの実施などが挙げられます。
ステークホルダーマネジメント(Stakeholder management)
ステークホルダーマネジメント(Stakeholder management)とは、企業内で実行されるプロジェクトにおけるステークホルダー全員を管理することです。
この場合のステークホルダーとは、そのプロジェクトの利害関係者のことを指し、プロジェクトメンバー、意思決定者やクライアントなどが当たりますが、企業によって定義が異なる場合もあります。
プロジェクトを実行する際には、多くのステークホルダーが存在するため、その個人や団体を明確にした上で、利害関係者全員を管理しながら、良好な関係を築くことがステークホルダーマネジメントの狙いになります。
その上で、企業の課題と優先順位を決めながら、ステークホルダーとの利害や損得を管理し調節していくことで、プロジェクトのスムーズな進行につながるでしょう。
(なおPMBOKではステークホルダーの定義を「プロジェクトやプログラム、ポートフォリオの意思決定、活動成果に影響したり、影響を及ぼされたり、影響を受けると感じる個人やグループ、組織」としています。『PMBOK 第6版 715ページより』)
プロジェクト管理においてステークホルダーマネジメントがなぜ重要なのか
プロジェクトには、社内・社外から役割や職能の異なるメンバーが集まることも多くあります。
企業や部署を超えて集まるメンバーは当然、利害関係も異なります。
そのような中で、プロジェクトに関わる人達の様々な利害関係や期待値を予め理解した上で、適切にコミュニケーションを取り、プロジェクトを進行していくことで、予期せぬトラブルや手戻り、プロジェクト後半においてのどんでん返しを防ぐことができます。
このような活動はステークホルダーマネジメントといわれることがあります。
今日では、働き方の多様化により、企業でのプロジェクトに参加するメンバーの関わり方や利害関係はさらに多様化しており、ステークホルダーマネジメントの複雑性・重要性がさらに増しているといえるでしょう。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
ステークホルダーマネジメントの基本

では、ステークホルダーマネジメントとは具体的に何をすればよいのでしょうか?
ステークホルダーを洗い出す
上述の通り、ステークホルダーマネジメントの第一歩は、プロジェクトに関わる利害関係者を洗い出すことです。
プロジェクトの作業をするメンバーだけでなく、資金や人員の提供を承認する役職者や外注先の会社、クライアントなど様々です。
そういったステークホルダーを漏れなく洗い出すようにしましょう。
その際に、ステークホルダーを直接的な関係者と間接的な関係者に分類すると洗い出しやすくなります。
直接的ステークホルダーの例
プロジェクトに直接関わり、利害関係のある人々
- プロジェクトメンバー
- プロジェクトの承認者・意思決定者
- 成果物を確認する関係部署
- 外注先
- クライアント
間接的ステークホルダー例
一時的ないしは間接的な関わりを持つ可能性のある人々
- プロジェクトメンバーの上長
- (プロジェクトメンバーではない)同僚
- 行政
- 地域住民など企業をとりまくコミュニティ
プロジェクト開始時点で、全ての関係者を洗い出すことは難しい場合もありますが、プロジェクトのはじめに一度洗い出しを行っておけば、それを意識しながらその後のプロセスを進められるようになります。
また、直接的ステークホルダーをマネジメントすることはもちろん、間接的ステークホルダーの理解を得つつ、予期せぬリスクをつぶしておくことは広義のステークホルダーマネジメントとして重要な活動であるといえます。
ステークホルダーの関わり方を明確にする
次に、洗い出したステークホルダーとの関わり方を整理します。
その際にいくつかの方法が考えられますが、例えば、以下のような軸を用いてステークホルダーを整理することが可能です
- プロジェクトにおける権力(権限)
- プロジェクトへの関心度
- プロジェクトへの関与度
- プロジェクトへの影響度
これらの軸を組み合わせて、マトリックスをつくりステークホルダーを分類することで、関わり方やコミュニケーションの内容・頻度を体系的に整理することができます。
ステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行う
ステークホルダーとの関わり方を定義した後は、実際にプロジェクトの進捗に合わせてステークホルダーとコミュニケーションをとっていきます。
一つ前の章で紹介した各ステークホルダーの分類を活用しつつ、コミュニケーションの頻度や方法を予め定義しておくと良いでしょう。
プロジェクトにおけるステークホルダーへのコミュニケーションは様々な方法がありますが、例えば以下のような使い分けが考えられます。
- プロジェクト内のタスクを担当するプロジェクトメンバー
プロジェクト管理ツール、チャットツールなどでのリアルタイムのコミュニケーション - タスクは担当しないが意思決定を行うプロジェクトオーナーなど
週1回の定例会議、ステアリングコミッティ - 直接プロジェクトには関わらない関係者(間接ステークホルダー)
議事録の共有やWikiの共有
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
Jootoでステークホルダーと円滑なコミュニケーションを

Jootoは誰でも簡単に使える、クラウド型タスク・スケジュール管理ツールです。
Jootoの基本的な使い方はドラッグ&ドロップ。
シンプルなかんばん方式で、ITツールに慣れていない人でも、直感的にストレスなくお使いいただけます。
かんばん方式ではタスク担当者がタスクやスケジュールを入力することで、業務が可視化され、自分以外の他のメンバーが今、どんなタスクを抱えているかひと目で把握することができます。
メンバーが何のタスクに取り掛かっているのか分かるので、円滑なコミュニケーションに役立ちます。
タスクごとにチャットやファイルの共有ができるのも大きな特徴。
情報が迷子になることがなくなり、コミュニケーションコストのカットに大いに役立ちます。
Chatwork・Slackとの連携ができるのも嬉しいポイント!
情報が一元化でき、確認にかかる手間を減らすことができます。
部署やチームを横断した管理も可能です。
小規模チームだけではなく、会社全体でJootoをご利用いただけます。
大企業向けタスクDX
従業員の数の多い大企業におすすめしたいのが「タスクDXプラン」です。
他のプランとは異なり、利用人数に応じて料金が変わるのではなく、ライセンスは無制限、ボード作成も無制限が「タスクDXプラン」のメリットです。
社内全体の従業員をフォローすることが可能となります。
多くの利害関係を調整することを求められるステークホルダーマネジメントは、非常に難易度が高く奥深い領域だと言えます。
プロジェクト管理に関わる方はぜひステークホルダーマネジメントの能力を高めて、さらにレベルの高いプロジェクト管理を目指しましょう。


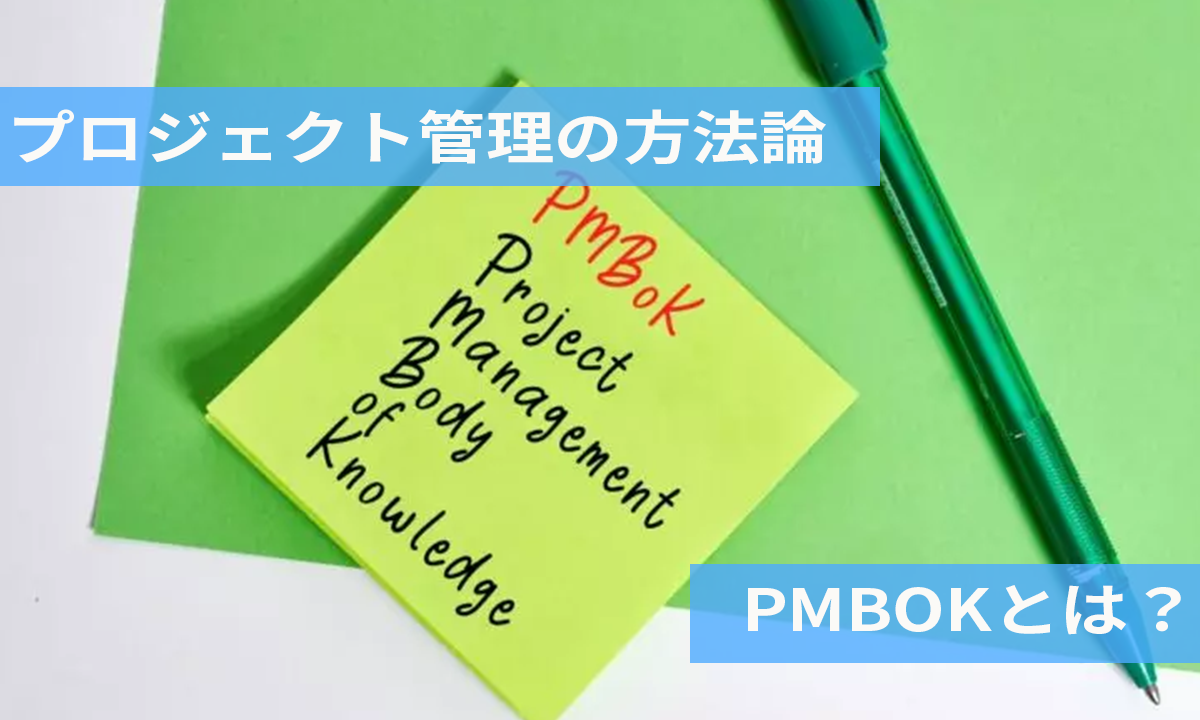

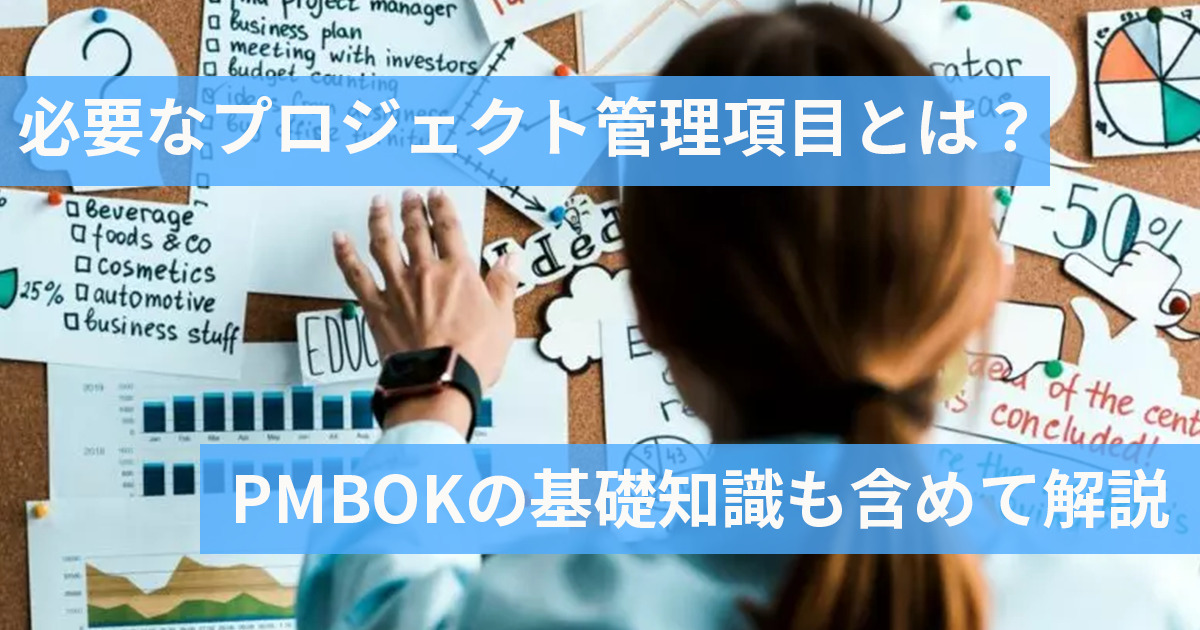
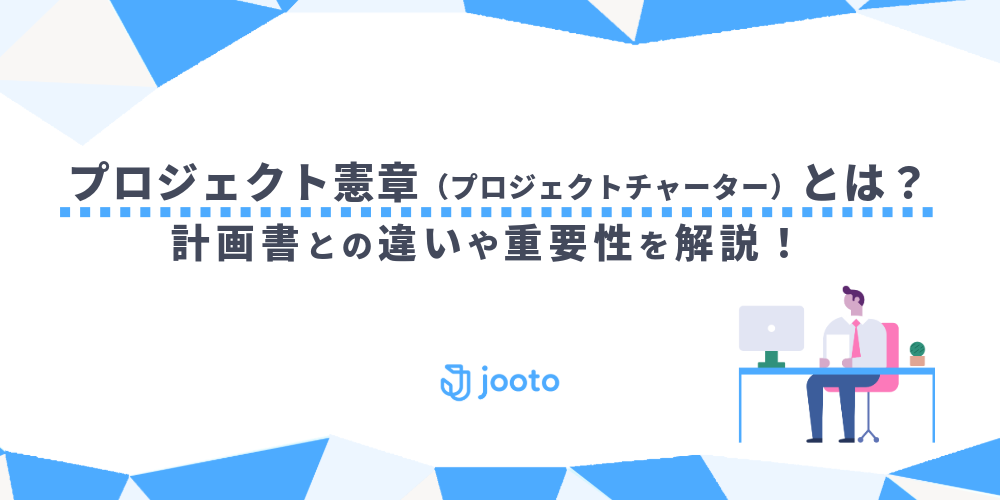

 © 2024 Jooto
© 2024 Jooto
Comments are closed.