プロジェクトを立ち上げる際は、プロジェクトの目的や内容を社内外の関係者に説明し、賛同を得るプロセスが必要です。
ここでつまずいてしまうと、プロジェクトに必要なリソースを十分に確保できず、プロジェクトの遂行自体が困難になるケースもあります。
プロジェクトの企画書とは、プロジェクトの詳細を凝縮して効果的に相手に伝えるための重要な文書です。
書き方や注意点を理解しないまま企画書の作成に取りかかると、自分のアイデアをまとめただけの文書になってしまうため、注意が必要です。
当記事では、企画書の書き方や作成に役立つフレームワーク、作成のポイントなどを解説します。
企画書の作成をより効率的におこなうための管理ツールも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
目次
プロジェクトの企画書とは
プロジェクトの企画書とは、新しいプロジェクトを立ち上げる際に実行プランを伝えるために作成する文書のことです。
英語では「proposal」と呼びます。
企画書には単にアイデアを書き記すのではなく、プロジェクトのスケジュールやコスト、目的、ゴールなどの具体的な内容を明記します。
企画書を作成する目的
企画書を作成する主な目的は、以下のとおりです。
- ステークホルダーの賛同を得る
- プロジェクトの実行に必要な資金を確保する
- 社内の人的リソースを確保する
プロジェクトの実行には、プロジェクトチームのメンバーだけでなく、社内外の関係者の賛同を得るステップが不可欠です。
口頭や簡易的な形式によって企画内容を伝えることも可能ですが、文書にまとめることで関係者に対して企画内容を効果的に周知できます。
企画書とプロジェクト憲章の違い
企画書と同様に、新しいプロジェクトを立ち上げる際に作成する文書としてプロジェクト憲章があります。
企画書とプロジェクト憲章の違いは、作成の目的です。
企画書を作成する最大の目的は、プロジェクトの必要性を伝えて関係者を説得し、賛同を得ることです。
これに対してプロジェクト憲章の作成目的は、プロジェクトの目的やスコープなどの詳細を整理し、関係者に周知することです。
そのため、基本的には企画書を作成して賛同を得たあとに、プロジェクト憲章を作成します。
企画書と提案書の違い
企画書と混同されがちな文書として、提案書があります。
提案書は、顧客の課題に対する解決策の方向性を提示するために作成します。
今後の方向性や必要なコスト、スケジュールなどを示すことが一般的です。
これに対して企画書は、より具体的なアクションプランを明記した文書といえます。
実務にまで落とし込んでプロセスやスケジュールを具体的に明記し、必要なコストも詳細に算出します。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
企画書の書き方

説得力のある企画書に仕上げるためには、必要な項目が網羅されていることが大切です。
記載すべき内容は、以下の7つです。
- エグゼクティブサマリー(導入)
- 現状分析・課題
- ゴールと全体像
- 企画内容の詳細
- スケジュール
- コスト
- 期待される成果物
それぞれについて詳しく解説します。
エグゼクティブサマリー(導入)
エグゼクティブサマリーとは、企画書のタイトルに続く導入部分のことです。
企画書の概要を簡潔にまとめるとともに、読み手が続きを読みたくなるような説得力ある文章にすることが大切です。
プロジェクトによって解決すべき課題や解決策、プロジェクトの実行によって期待される成果物などを記載するのが一般的です。
現状分析・課題
「プロジェクトの必要性」や「どのような問題点があるのか」を現状分析をもとに論理的に説明します。
読み手を説得するためには、主観的な意見だけを伝えるのではなく、客観的なデータをもとに説明することが大切です。
市場の動向などの外部環境と、社内のリソースの配分などの内部環境の両軸から現状を分析します。
現状分析および課題のパートは企画書の中核であるといっても過言ではありません。
後述するフレームワークを活用して説得力のある内容に仕上げましょう。
ゴールと全体像
企画のゴールと目的を具体的に明記し、全体像を明らかにします。
現状分析によって浮き彫りになった問題点をどのような手段で解決し、最終的にどのような状態を目指すのかをわかりやすく記載します。
企画内容の詳細
企画の具体的な内容を明記します。
企画の「コンセプト・ターゲット・プロセス・ツール」の4つを具体化し、目的を達成するためのロードマップを具体的に提示することがポイントです。
例えば、「30〜40代の子育て世代の女性をメインターゲットとして主にインターネット広告を活用したプロモーション活動を実施する」などと記載します。
このパートでは、企画の中身が読み手にしっかり伝わるように詳しく書くことが大切ですが、項目を盛り込み過ぎて、核心部分が伝わりにくくなってしまっては逆効果です。
プロジェクトのスコープに応じてある程度項目を絞ることも大切です。
スケジュール
プロジェクト全体のスケジュールを記載します。
納期から逆算して時間の配分を考えることが大切です。
外部環境や社内状況の変化によってスケジュール通りにプロジェクトが遂行できないケースも想定されます。
そのため、スケジュールにはある程度の余裕を持つことが大切です。
コスト
プロジェクトの遂行に必要なコストについて説明します。
「どの程度の予算を投じて、どのくらいの期間で回収できる見込みか」を明記します。
コストを見積もる際は、項目ごとに細かく算出することで、あとから予算不足に陥るリスクを回避できるでしょう。
具体的な支出項目としては、人件費や材料費、輸送費、広告費などがあげられます。
関係者の賛同を得るためにも、これらの内訳を明確にすることが大切です。
期待される成果物
最後にまとめ部分として、プロジェクトの実行によって期待される成果物を記載します。
エグゼクティブサマリーとのバランスを考慮し、簡潔に締めくくることが大切です。
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
企画書に役立つフレームワーク

企画書は、アイデアを思いつくままに書き連ねただけでは用をなしません。
読者を納得させるだけの論理性が不可欠です。
企画書を書く際は、以下のようなフレームワークを活用して情報を整理しましょう。
- 3C分析
- SWOT分析
- 6W2H
それぞれについて詳しく解説します。
3C分析
3C分析とは、企業を取り巻く環境を明確にし、今後の事業戦略を導くために用いられるフレームワークです。
以下の3つの要素を分析します。
- Customer (顧客)
- Competitor (競合)
- Company (自社)
3C分析をする際は、最初にCustomer (顧客)を分析します。
近年のマーケティング活動は、顧客重視で進める必要があるためです。
次に、Competitor (競合)を分析します。
競合他社の売り上げ状況や社員数、市場シェアなどを明らかにしたうえで、競合のサービスや製品の強みと弱みを分析します。
最後に、Company (自社)の分析です。
経営資源や業績、市場シェア、収益率、組織力など、多様な視点から自社を分析することが大切です。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社の内部環境および外部環境を4つの視点から洗い出し、分析する手法です。
企業や事業の置かれている状況を知るために用いられます。
SWOTとは、以下の単語の頭文字を取ったものです。
- Strength(強み)
- Weakness(弱み)
- Opportunity(機会)
- Threat(脅威)
SWOT分析をする際は、最初に分析の目的を明確にすることが大切です。
SWOT分析は複数人で取り組むことが一般的ですが、目的が漠然としていると各人でとらえ方に差が生じてしまい、効果的な分析ができません。
具体的には、「企業のブランド価値を最大化する」といった抽象的な表現ではなく、「ブランドの認知度を高めることで売上高を20%増やす」などと設定することで、分析の精度を高められます。
6W2H
6W2Hとは、マーケティング領域やコミュニケーションでよく活用される情報伝達のフレームワークです。
6W2Hを意識することで、必要な事項を漏れなく読み手に伝えられます。
6W2Hの具体的な内容は、以下のとおりです。
- When:いつ実施するのか(実施時期や全体のスケジュール)
- Where:どこで実施するのか(市場)
- Who:誰が実行するのか(プロジェクトの実行者やステークホルダー)
- What:何を実施するプロジェクトなのか(ゴールや成果物、企画内容)
- Why:なぜ実施するのか(企画の背景や現状分析)
- Whom:誰に対して実施するのか(企画のターゲット)
- How:どのように実行するのか(実行手段や方法)
- How much:どのくらいの費用が必要か(収支計画)
タスク・プロジェクト管理を
シンプルにわかりやすく
Jootoはカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。
直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴です。
まずは無料で体験してみる
企画書作成のポイント
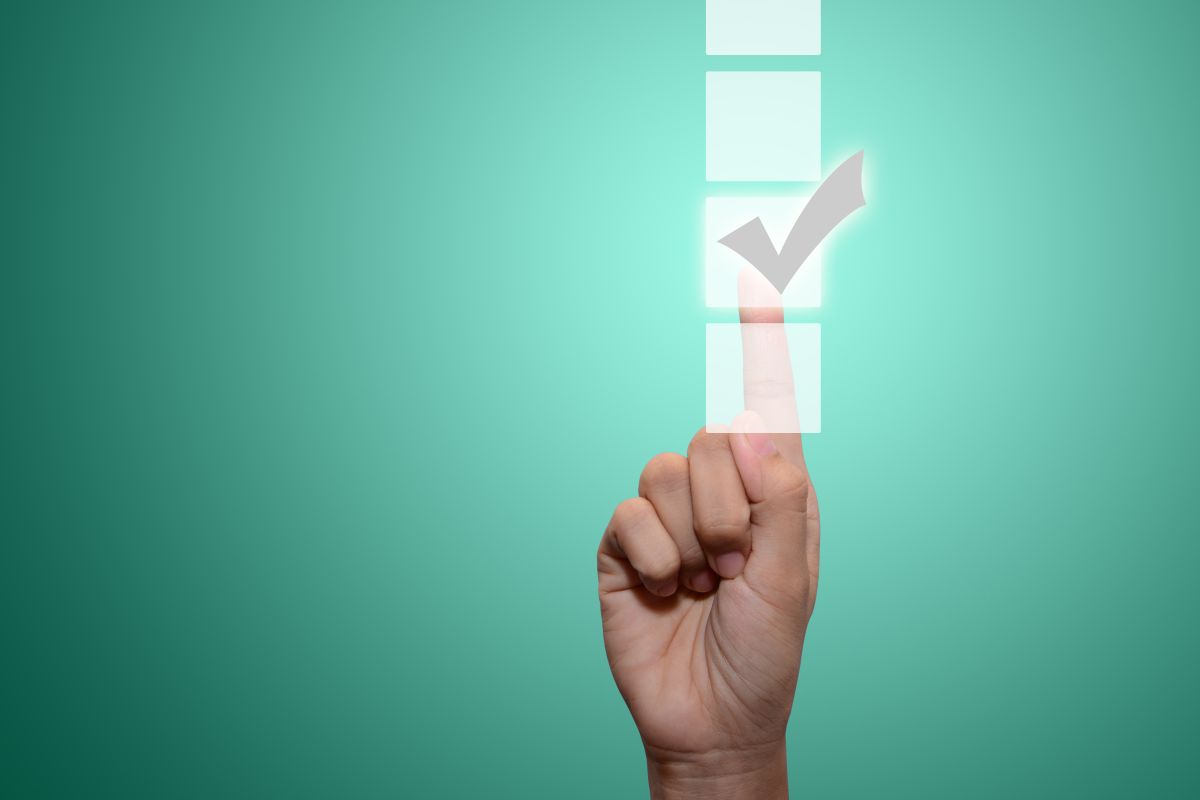
読み手を納得させられる企画書を作成するためには、いくつかのポイントがあります。
ポイントは、以下の4つです。
- 書く前の準備を丁寧におこなう
- 読み手に対する説得力を意識する
- 簡潔にまとめる
- 図やグラフを活用して視覚的に訴求する企画書に仕上げる
- 管理ツールを導入する
それぞれについて詳しく解説します。
書く前の準備を丁寧におこなう
企画書を書き始める前に、企画の方向性やメインターゲットを明確にする必要があります。これらが曖昧なまま作成に取りかかると、作成途中でコンセプトがブレてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
また、企画書の作成ツールも事前に決めておきましょう。
企画書はMicrosoft PowerPointやKeynoteを使用して作成するのが一般的です。
インターネット上のテンプレートをダウンロードして利用することで、企画書の作成を効率化することも可能です。
社内で企画書のフォーマットが決められている場合は、ルールに則って作成します。
読み手に対する説得力を意識する
企画書は、関係者がプロジェクトやプロジェクトチームに対する理解を深め、賛同してもらう目的で作成するため、説得力が重要です。
説得力を持たせるためには、前述したフレームワークを活用するなどして、論理的でわかりやすい構成を意識する必要があります。
客観的な事実やデータを収集し、分析する手間を惜しまないようにしましょう。
簡潔にまとめる
企画書を作成していると、つい多くの情報を盛り込みたくなってしまうかもしれませんが、情報量が多すぎると、プロジェクトの要点がぼやけてしまい、読み手に訴求しづらくなってしまいます。
企画書の読者は、管理職や経営層などの忙しい立場にある人がほとんどです。
相手の貴重な時間を奪わないためにも、要旨をシンプルにまとめることが大切です。
図やグラフを活用して視覚的に訴求する企画書に仕上げる
テキストだけで埋め尽くされた企画書は、見るだけで読み手にストレスを与える恐れがあります。
適宜図やグラフを挿入することで、視覚的に情報を伝えることができ、スムーズに読み進められるでしょう。
定量的な根拠に基づく企画書は、説得力を向上させる効果があります。
テキストと図やグラフとのバランスを意識して作成しましょう。
管理ツールを導入する
企画書に記載すべき内容は多岐にわたり、すべてを網羅したうえで簡潔かつわかりやすい企画書を作成することは容易ではありません。
過去に企画書の作成に取りかかったものの、途中で手が止まってしまった経験のある方も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、管理ツールの導入です。
プロジェクトの概要から自動的にタスクを洗い出す機能を備えた管理ツールを導入すれば、洗い出されたタスクの内容を企画書の詳細に反映させることができるでしょう。
Jootoの「AIタスク生成β版」を活用して企画書の作成を効率化しよう

Jootoは使いやすさを追求したクラウド型のタスク・プロジェクト管理ツールです。
基本操作はドラッグ&ドロップだけで、誰でも簡単に使いこなせます。
Jootoの「AIタスク生成β版」はプロジェクトの立ち上げをよりスムーズにすることを目的として開発されました。
プロジェクトの概要を入力するだけで、AIがタスクと最適な管理ボードを自動的に作成します。
例えば、新しいシステムを開発する場合は、システム開発に必要な情報収集からリリース後の販促活動までに必要なタスクを網羅したプロジェクトボードを自動で作成可能です。
タスクを洗い出す作業やタスクの依存関係を考慮しながらタスクの順序を考える時間が削減され、大幅に作業効率がアップします。
「AIタスク生成β版」は、企画書を作成する際にも効果を発揮します。
「AIタスク生成β版」によって作成されたタスクの内容をもとに企画書の詳細を作成すれば、必要な事項が漏れなく含まれた企画書が簡単に完成するでしょう。
プロジェクトの全体像を視覚的に把握できるため、スケジュールの目途も立てやすくなります。
企画書の作成業務を効率化したいニーズがある場合は、タスク・プロジェクト管理ツールJootoの導入をぜひご検討ください。


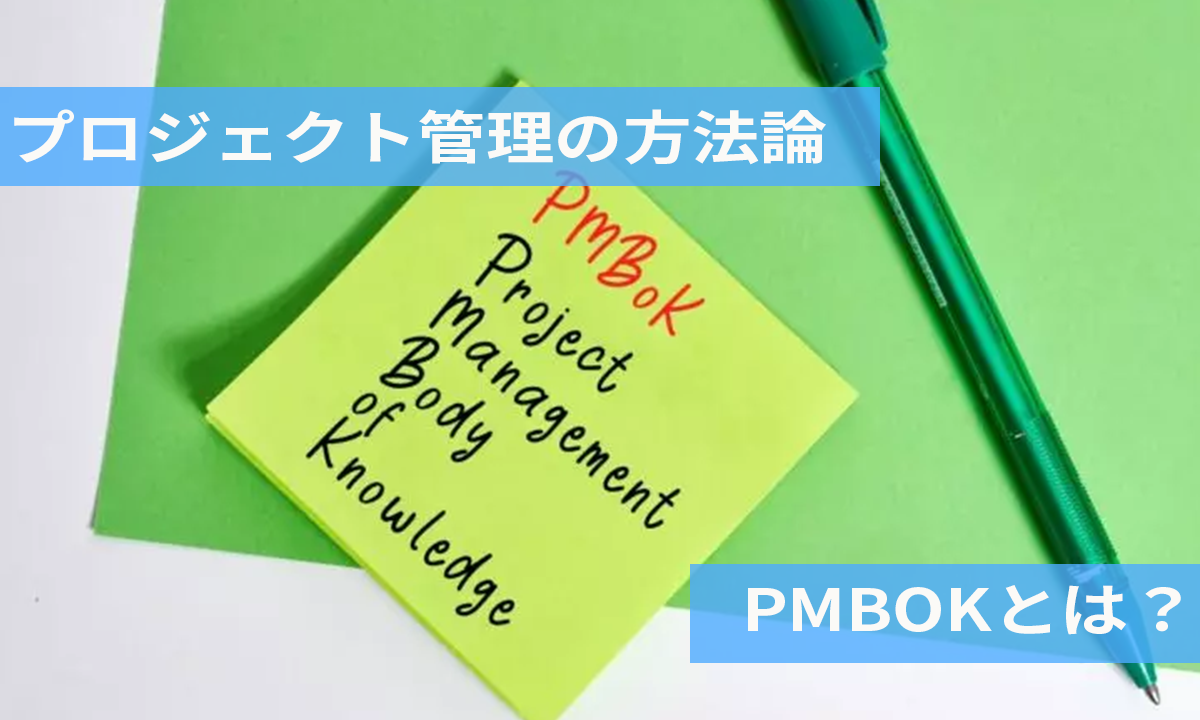
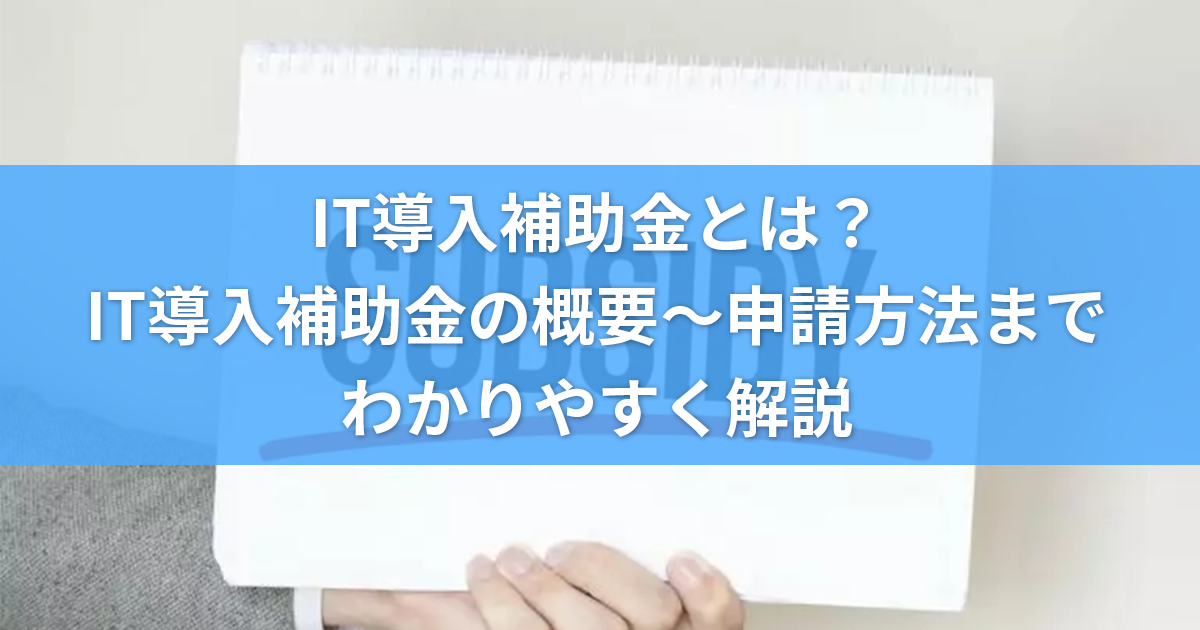
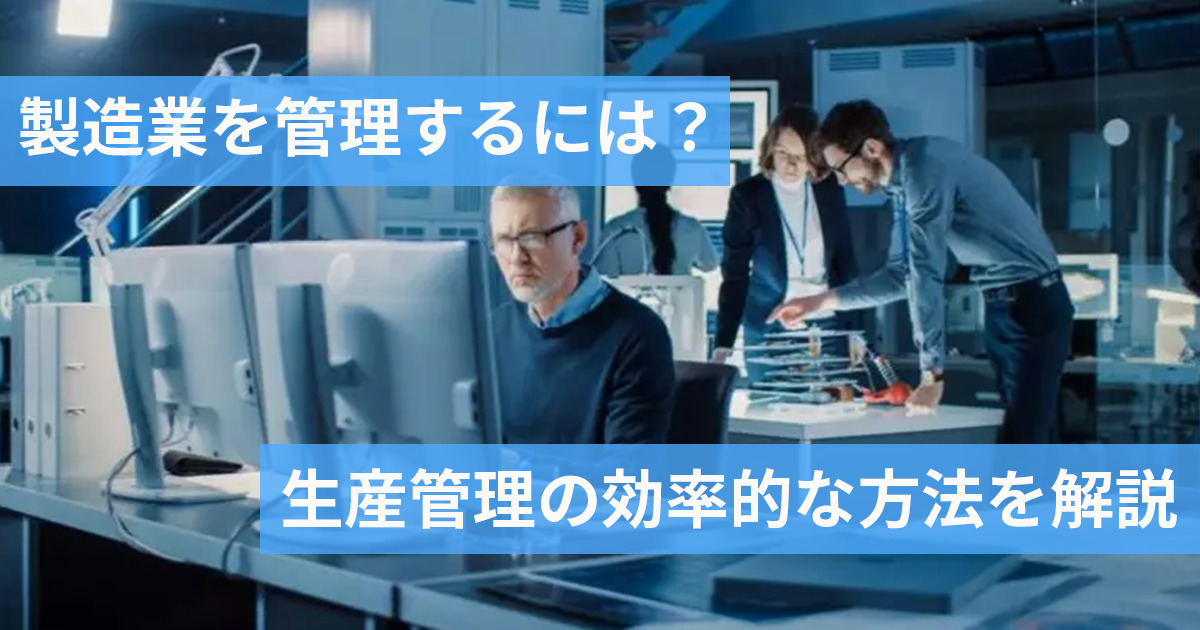
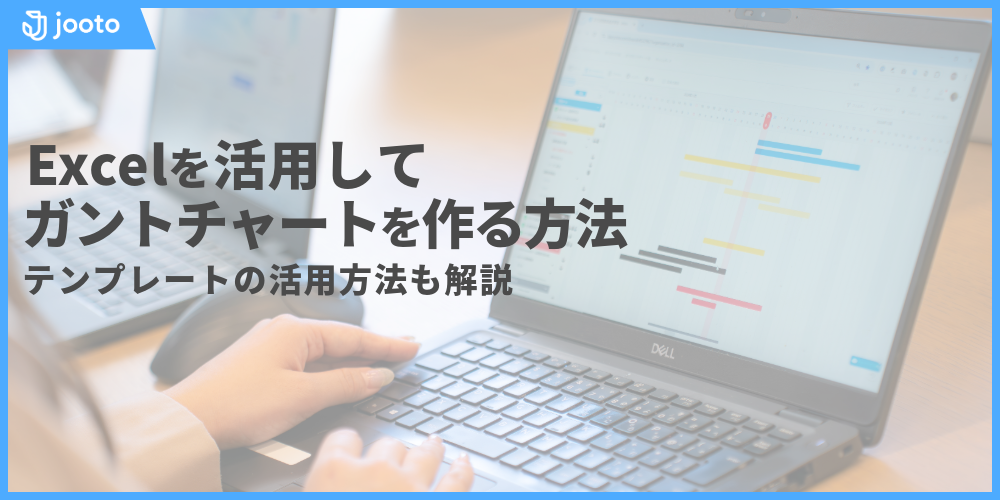

 © 2024 Jooto
© 2024 Jooto
Comments are closed.